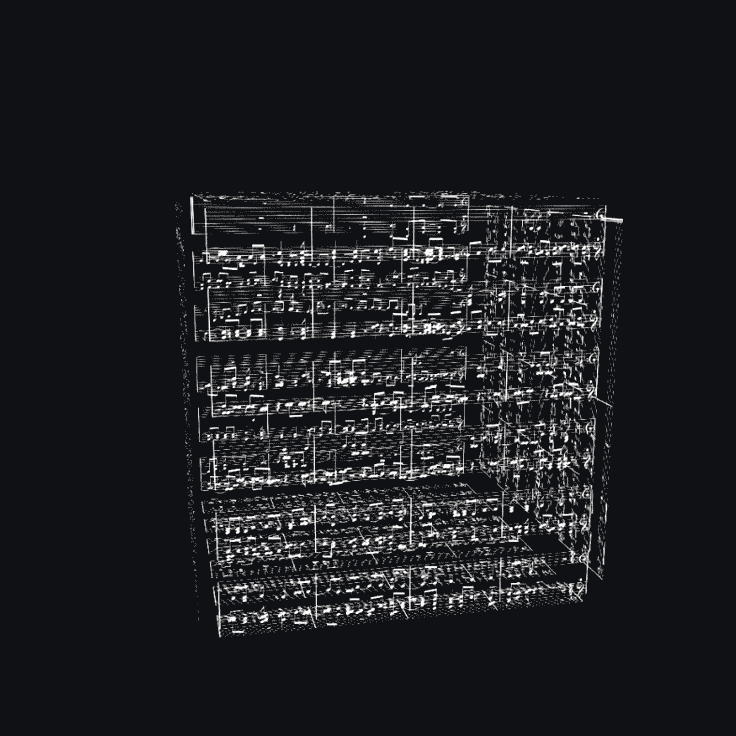湿囘
20240807
重い睡気の中から少し身を乗り出してみると、どうやら、音がしない程度の淡い雨が降っている。いまいち体温も上がらないわけだ。時刻は……時計を確認するまでもなく、本来の予定を遂行するためのそれはとうに死んでいることを部屋の空気が伝えていた。昨日も一昨日もそうだったが、ここにあるのは中途半端な慣れで、当為に蔑まれていることにはいつでも気がつけるのだ。
︙
そのまま、輝度を最低にした部屋は依然としてその配置を変えなかった。しかし暫くすると、そろそろ食糧が尽きるといって、眩暈をやり過ごした僕は身体を外へと押し進めるのを始めなければならなくなった。
実際は、少なくとも今日は外に出さえすればどうってことはなかったし、空を見れば、雨は傘をさすほどのそれではなかった。遠くのアスファルトに目を遣ると、中学生くらいの2人組が帰路にのって、その後ろから青い車が来ている。それに気がついた片方──それは道路脇のほうにいた──がもう片方の腕を引っ張って端に寄り、他愛もないであろう話を続けていった。僕はそれを観たあと、再び下を向いた。
必要最低限の食糧だけを買って家に帰った時には、もう辺りは暗くなり始めていた。これから夜が始まるらしかった。当然今日も眠れないだろうと推測されるので、大して集中もできない現状でどう時間を潰していくかを考える必要があった。起きた時には多少あったはずの食欲もすっかり消え失せてしまったし、本来やるべきだったことなどはもうだいぶ手遅れだ。僕は、いつか入院していたときの光景を第三者の視点で思い出していた。それと同じような退屈がここに安寧と空白を供えていくのも、やはり第三者の視点で────眺めている。ここは白くない。